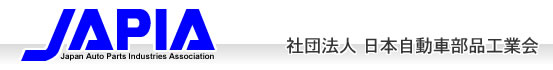【第12回】 三輪修氏(金属工作機械工・デンソー技研センター)
「学校でも、職場でも、どこへ行っても、人間関係に恵まれたからです」
 第12回は、デンソー技研センターの三輪修(みわ・おさむ)さんです。三輪さんは愛知県出身の1951年9月生まれの58歳。主に金属工作機械工の技能や知識を磨き、その後、デンソーの職業訓練指導員として後進の育成に関わり、多くの訓練生を職場に送り出すなど、技能訓練分野の第一人者です。67年4月日本電装(現デンソー)に入社、デンソー訓練生として3年間、仕上げ工、金属工作機械工の基礎技能や知識を学んだ。70年4月工機部型課、2001年1月デンソー技研センター・短大教育室工高高専課グループリーダー、05年1月同・技能研修部部長、06年1月同・短大教育部部長などを経て、07年1月技能開発部部長。一方、1976年12月国家技能検定1級フライス盤作業成績優秀で技能検定協会会長表彰、80年5月同1級精密器具製作成績優秀で職業能力開発協会会長表彰、2000年11月認定職業訓練事業の推進功労で愛知県知事表彰、03年11月愛知県優秀技能者表彰など数々の栄誉に輝き、06年11月には同年度の「現代の名工」に認定され、09年度春の褒章では黄綬褒章を受章されています。
第12回は、デンソー技研センターの三輪修(みわ・おさむ)さんです。三輪さんは愛知県出身の1951年9月生まれの58歳。主に金属工作機械工の技能や知識を磨き、その後、デンソーの職業訓練指導員として後進の育成に関わり、多くの訓練生を職場に送り出すなど、技能訓練分野の第一人者です。67年4月日本電装(現デンソー)に入社、デンソー訓練生として3年間、仕上げ工、金属工作機械工の基礎技能や知識を学んだ。70年4月工機部型課、2001年1月デンソー技研センター・短大教育室工高高専課グループリーダー、05年1月同・技能研修部部長、06年1月同・短大教育部部長などを経て、07年1月技能開発部部長。一方、1976年12月国家技能検定1級フライス盤作業成績優秀で技能検定協会会長表彰、80年5月同1級精密器具製作成績優秀で職業能力開発協会会長表彰、2000年11月認定職業訓練事業の推進功労で愛知県知事表彰、03年11月愛知県優秀技能者表彰など数々の栄誉に輝き、06年11月には同年度の「現代の名工」に認定され、09年度春の褒章では黄綬褒章を受章されています。
■「好きこそものの上手なれ」
三輪修さんから話を伺っていたら、こんなことわざが浮かんできた。「好きこそものの上手なれ」。岩波ことわざ辞典によれば、江戸時代中期頃から各種文献に用例がみられることわざで、その意は「好きであることが物事の上達の道だということ。一般に芸事や習い事は、好きになると関心が深まり、それに割く時間も長くなり、結果として腕前が上がるものである。もちろん、下手な横好きということもあるが、嫌いが上手になる可能性は低いということだけは言えよう」とある。三輪さんのものづくり人生を支えてきたキーワードの一つでもあろうか。
なかなか向こう意気の強そうな一面もある三輪さん。「入社試験に落ちたら、高校に行こうかと思っていました」。"15の春"特有の気負いもあったろうか。以来、43年。この間、デンソーの職業訓練指導員として多くの訓練生を職場に送り出す一方、研修教材の開発、専任職(エキスパート)昇進前評価試験課題の開発、障害者への技能指導、技能五輪選手の育成など、技能訓練分野に数々の業績を積み重ねてきた。そんな業績が認められ、2006年秋の「現代の名工」認定に続いて、09年秋には黄綬褒章の栄誉にも輝くなど、ものづくりの世界では頂点を極めた方である。「いやいや、学校でも、職場でも、どこへ行っても、私は人間関係に恵まれたからですよ」と、謙遜しきりの三輪さんだ。
父親が屋根を葺く職人の三輪さん。生まれ育った環境からか、子供の頃からものを作ったり、絵を描いたりするのが、大好きな性分だったという。もっとも、そこにはそれを促す手先の器用さなど、天性の素質も加わったに違いない。そして、それに一段と拍車がかかったのは、小学2年生の時だ。きっかけは、自身が制作した粘土細工だ。ひょっとすると、これを境に、三輪さんのものづくり人生に向けてのレールが敷かれていったのかもしれない。
■『上手いぞ』と、先生に誉められて

「今でも、鮮やかに覚えていますね。小学2年生の時です。担任の先生から粘土細工が『上手いぞ』と大変誉められましてね。先生の誉め方も上手だったのかな。すっかり乗せられてしまって。つい、自分でも上手いのかな、とその気になりましてね」。担任の先生は、三輪さんの素質を見抜いていたのか。それからというものの三輪さんは、ますます図画工作の授業が好きになったという。「確か、担任の先生は、社会科が専門でした。でも、その先生からは、絵の具の使い方なんかも教わりましてね。素晴らしい先生に出会ったと思っています」。懐かしそうに振り返って見せる。
ものづくりへの関心が次第に、膨らんでいく。中学生の頃には、ものづくりの世界に進もうと考えるようになっていた。「日本電装(現デンソー)の入社試験を一緒に受けないか」。同級生の一人から声をかけられたのは中学3年生の時だった。「その頃には、ものづくりの仕事に就きたいと考えていましたから、じゃ、一緒に受けようかとなりました。会社ですか、当時はどこでも良かったと思っていました」。迷うこともなく、ものづくりの世界へ一直線に突き進んだという。
■技能が認められ技能五輪選抜メンバーに
もちろん、入社試験には合格した。1967年4月、三輪さんは技能者養成所本科(現デンソー工業技術短期大学校工業高校課程)に訓練生として入社、ものづくり人生のスタートを切った。訓練期間は3年。仕上げ工の基礎技能やその裏付けとなる知識などを中心に具体的にものづくりのイロハを学んでいった。その訓練期間の2年目が終わろうとしていた頃、思わぬ声がかかった三輪さん。習得した技能や学ぶ姿勢が高く評価され、三輪さんは技能五輪大会の選抜メンバーに選ばれたのだ。
「ただ、選抜メンバーの先輩らの実習を見学した時には、そのレベルの高さにびっくりしました。凄いな、とも思いましたよ。で、自分にも同じようにできるのか、という不安も芽生えましたね」。喜びと不安とが複雑に同居する中、三輪さんら選抜メンバーの技能鍛錬が始まった。「実際、鍛錬は厳しかったですよ。ただ、鍛錬を通じて技能が磨かれていきましたから、磨かれていく楽しさというのも体験できましたね」。そして、技能五輪全国大会のフライス盤部門に出場、第4位に入賞するという快挙を成し遂げた。そればかりか、日本産業訓練協会会長表彰と日本電装(現デンソー)社長表彰のダブル受賞に輝き、ものづくり人生が大きく飛躍していくチャンスをつかんだのだ。
70年4月、工機部型課へ。三輪さんはそこで、型製作の一員として技能五輪の選抜メンバー時代に磨いた技能や知識を業務にフルに活用、さらに実践的な技能練磨に励んだ。例えば、模型や型板に倣いながら工作物を削っていく最新型倣いフライス盤で新製品として開発された自動車の「メータケースモールド型加工」の担当を任され、フライス盤の卓越した技量を発揮し、加工熱や工作物の締め付け力など、ヒズミを考慮しながら5-10μmの精度で型部品と型製作を行うとともに、型の角度加工に対応できる「角度つき刃具」を開発するなど、高精度な型製作の実現に大きく貢献したという。「通常は、この加工に半日くらいはかかっていましたが、それを1時間くらいの加工時間に短縮したわけです」。三輪さんにとっての自信作の一つだ。
■次々と新機軸を技能訓練分野に積み重ねる
72年2月、日本電装工業高等学園(現デンソー工業技術短期大学校)指導課に異動。以来、一貫して後進を育成する技能訓練分野に取り組んでいく。具体的には、設備の総合制御能力を高める「専用機総合組み立て教材の開発」、技能の高度化と伝承に貢献する「エキスパート昇進前評価試験課題の開発」、受講者の理解度に合わせたペースで進められる「空気圧研修教材の改良」など、技能訓練分野に数々の新機軸を打ち立て、後進の育成に大きく貢献した。同時に、26年間の職業訓練指導員として3500人の訓練生を育て上げるとともに、障害者技能五輪大会(アビリンピック)などを通じての障害者への技能指導、さらには技能五輪選手の育成など、職業訓練指導者としての実績も重ねた。
とりわけ、1998年度に高度熟練技能者を対象に専門技能の向上と技能伝承を図る目的でデンソーが創設した「エキスパート昇進前評価試験制度」。三輪さんは、その前段の昇進前評価試験委員を委嘱され、公平で客観的に評価できる「エキスパート昇格前試験課題」を開発、技能の高度化や技能伝承に大きな役割を果たしたという。「現場のエキスパートクラスの全体的なレベルアップをどう図っていくかに腐心しましたね」と、苦心の一端を披露する。
■「職業訓練教材コンクール」で厚生労働大臣賞も受賞
厚生労働省主催の「職業訓練教材コンクール」で厚生労働大臣賞を受賞した「空気圧研修教材の改良」。これまでの教材は、空気圧機器の名称、構造、日本工業規格(JIS)記号の取得などが主流で、空気の流れや機器動作の確認、設備の正しい操作、日常点検、異常対応の教育などが難しかったという。このため、講義型研修では、受講者の職種、経験、能力などの面で基礎知識にバラツキがあり、全員に同じように理解させることには無理があった。
三輪さんをリーダーとするチームはそこで、各受講者のレベルに応じたペースで研修が進められる"自学自習型"に改良することを計画、①マルチメディア教材を活用して的確にフォローができる個別指導②生産設備に対応した制御部、動作部の実習教材を使用③空気の流れのアニメーション化を具体化するなど、教材を抜本的に改良した。その結果、職場から「設備の正しい操作、日常点検、異常時の適切な処置方法など、研修生の理解度が向上した」と評価された。三輪さんをリーダーとするチームの教材開発レベルの高さを社内外に証明した具体例の一つだ。
■油絵の世界でも才能に磨きをかける

JR東海道線「刈谷駅」からクルマで約15分の安城市高棚町のデンソー高棚製作所の一角にある「デンソー技研センター」。その1階応接室の壁に掲げられている縦横それぞれ1メートルほどの大きさの油絵。素人目には温かい色づかいが印象的な静物画だ。作者は今回ご登場願った三輪さんだ。「21歳の頃からずっと油絵を描いています。楽しいですよ」。油絵も、三輪さんが人生を歩んでいく上で欠かせないバックボーンの一つだ。ちなみに、三輪さんは洋画・工芸の美術団体「光風会」に所属し、同会主催の美術展には入選7回を数える経歴の持ち主である。油絵画家としても、プロ級の腕前だ。「牡丹散(ちつ)て打(うち)重(かさな)りぬ二三片(ぺん)」(与謝蕪村)。画家でもある与謝蕪村の代表的な句の一つである。三輪さんとどことなく重なる面も。山本健吉の「俳句鑑賞歳時記」によると、この句は「ある静止した時間を捉え、牡丹の花の本意をいかんなく描きつくしている。琳派の障?画(しようへいが)でも見るようで、花の王者らしい品位を見せている」と評されていて、物事の本質に迫っていく気迫がうかがえようか。それはものづくりの世界にも通じる作ることへの貪欲さでもあろう。